ロシアってなんであんなに大きいのか?という疑問が昔からありました。
良さそうな本があったので読んでみました。
ロシア人の起源は東スラヴ人で、ウクライナ人、ベラルーシ人に分化する前の民族として居住していました。
建国は862年か882年で、どちらにするかは決定してないようです。
ロシアという名称は15世紀ぐらいからだそうで、このころはルーシとかキエフ・ルーシとかの名称でした。
居住範囲はウラル山脈の西側に日本よりちょっと大きい範囲にいたそうです。
周りに大国(ビザンツ帝国など)がいくつもあったので、交流やお手本にしながら少しずつ国を強くしていきましたが、強くなるに伴い内乱が起こるようになります。
内乱により中心地であるキエフが衰退し、東の方に移動することになりました。
東には「不敗神話」のモンゴル帝国がはびこっておりルーシも当然脅威にさらされます。
戦いに負けて、そこから240年もの間モンゴルの支配下に置かれます。
これを「タタールのくびき」というそうです。
タタールはモンゴル、くびきは牛や馬などの家畜の首の後ろにあてる横木のことだそう。
解放されたのは14世紀。
16世紀にイヴァン4世がツァーリ(君主)となり、改革・戦争・テロの目白押しで周りから恐れられる強国になりました。
ついた異名がイヴァン雷帝。
このイヴァン雷帝の代で、モンゴル帝国の各国(カザン・ハン国、アストラ・ハン国、シビル・ハン国)を併合していき、シベリア進出の道をひらきました。
ここで一気に領地が広がりました。
その後も各方面に徐々に侵攻し、あんなに大きくなったようです。
でも、ずっと順当にいったわけではなく「タタールのくびき」以外にも、
リトアニアに南西部(ウクライナとベラルーシ)を奪取されたり、
(ロシアとウクライナとベラルーシに相違が生じたのはこの頃からと言われています)
モスクワがポーランドの支配下に置かれたり。
特にモンゴルにはトラウマがあるようで、アジア人に対して劣等感や羨望などがあっただろうと書かれています。
で、何度も支配下に置かれつつもあんなに大きくなったのに、歴史的に「世界一」になった時期がない(多分)。
ちなみに、プーチンが無名ながら大統領に選ばれたのは、ソ連崩壊後からロシアの低迷が続くなか「強いロシアの復活」を掲げたことが要因と。
なので、プーチンは強気の姿勢を変えるわけにはいかない。
劣等感に大統領になった経緯がからみ、国際社会を敵に回すようなことをする国になってしまったのかなと。
北朝鮮にしかり、ロシアにしかり、個人においても、劣等感というのは扱いを間違うと悪い方向に行くんだなと勉強になりました。
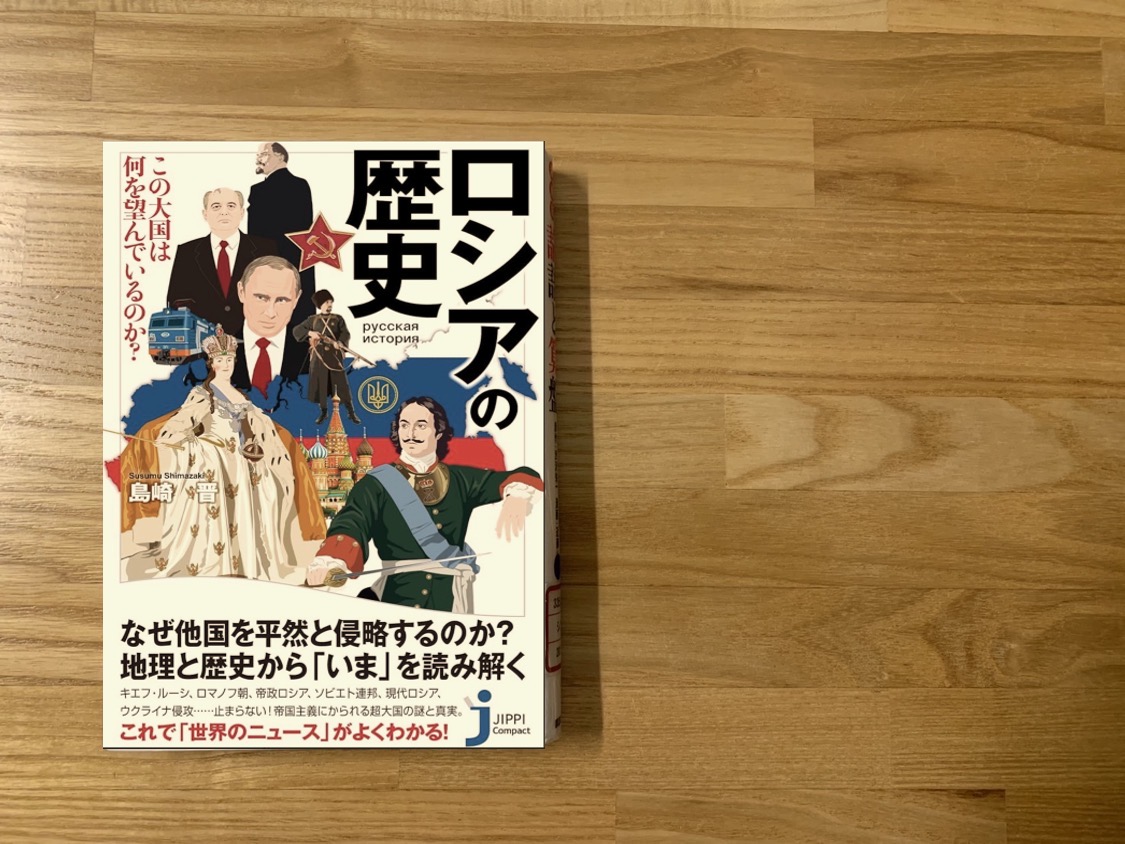

コメント